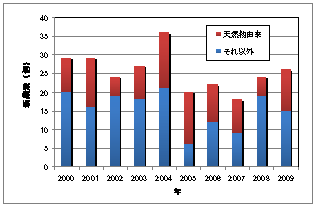|
2010年11月29日 《執筆者》 伊藤 勝彦
今年2010年は国際生物多様性年に当たる。そして、この10月には名古屋で記念すべき「COP(Conference Of the Parties)10」が開催された。COPとは1992年に結ばれた「生物多様性条約」や「気候変動枠組条約」などに参加した国の締約国会議のこと。生物多様性条約は今回で10回目を迎えるので、COP10と呼ばれる。 このCOP10、国内で初めて開催されたこともあり多くのメディアが取り上げた。そのため、その重要性を多くの人が認識されたのではないだろうか。良い機会であるので、ここでは薬と生物多様性について考えてみたい。 薬の歴史を紐解くと、その起源は動植物や鉱物である。そして、現在でも臨床の場で使用されている薬剤も多いことがわかる。代表例としてはモルヒネ、アスピリンが挙げられる。これらの薬物が純品の化合物として供給されるはるか昔、すでにモルヒネ、アスピリンについては起源植物自体やその煎じ薬は使用されていたという記録が残されている。驚きばかりである。痛みからの解放を望む気持ちは古今東西を問わないようである。 20世紀に入ると、科学の進歩によってペニシリン、スタチンなど細菌由来の薬剤が多く発見されることになる。その延長で、20世紀後半には遺伝子工学の進展や分析機器の高度化、そして特に1990年からのコンピューター科学の発展は著しく、コンピューター抜きでは創薬は語れないという研究者も多い。これらの創薬ツールの進化は、創薬手法を大きく変え、過去のように天然物への依存度は低くなっているのかと想像させる。 そこで、米国食品医薬品局(FDA)が2000年から2009年までの10年間に承認した新薬のうち、天然物由来の薬剤がどのくらい含まれているかを検証してみた (図1)。FDAを選んだのはこの10年間で最も多くの薬剤を承認しているからである。 直近の10年間でFDAが承認した薬剤の総数は255、このうち天然物由来として数えた薬剤は100であり、全体の39%を占めていた。そして、2000年から04年までの前半と05年からの09年の後半で数の差はなかった。ちなみに前半は51、後半は49である。この10年間においても、創薬に対する天然物由来の物質の貢献度は、平均して高いことがわかった。生物の多様性が重要であることに他ならないと考える。
図1.米国食品薬品局(FDA)の承認新薬数
出典: FDAのデータを基に著者が作成
最も多かったのはホルモン、プロスタグランジンなどの動物由来の薬剤で58、ついで微生物由来の37、植物由来は5であった。微生物由来では放線菌からの化合物が多かった。今後もこの傾向は引き続き続くであろう。今回は天然物由来の薬剤として、 ① 自然にある動植物、微生物などから抽出、構造決定された天然化合物、 ② 天然化合物由来の化合物の構造を基にした誘導体、 とした。 そして、ホルモン、オータコイド、サイトカイン、インターフェロンなどの生理活性物質および核酸塩基の誘導体生理活性物質に対する抗体も含めた。 日本の研究者は、古くは1900年の高峰譲吉博士らがアドレナリン、1910年の鈴木梅太郎博士によるチアミンの発見、その後も1973年の遠藤章博士のコンパクチンなど、多くの薬の基になる化合物を発見してきた。最近では、冬虫夏草から抽出された化合物を基に創製したFTY720(田辺三菱製薬)が、FDAの承認の勧告を受けた多発性硬化症治療薬として注目をあびている。 生物が多様性を持っているからこそ、生態が保たれている。薬という限られた分野であっても生物の多様性が多くの有用性のある薬剤や薬剤を創製する基になっている。現在でもそのことは変わりない。現在、多くの種が地球上から消えていると聞く。生態系の保全を祈るばかりである。
|